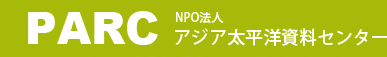2011年1・2月号
- A4版変形 56頁 800円+税

特集 まちがいだらけの「魚食文化」
魚や貝、甲殻類など、海の恵みは古くから日本の食卓を彩ってきた。しかし現在、これら水産資源の枯渇が世界的に懸念されている。気候変動の影響なども指摘されるが、その大きな原因は乱獲だ。
本来、水産資源には自然の営みの中で子孫を残し、再生産し続ける力がある。しかし、その力を上回る量の資源が、世界中の海で獲られ続けているのである。将来にわたって魚を食べ続けていくためには、漁獲量の規制をはじめとする管理が早急に必要だ。
2010年、様々な国際会議の場で、日本の魚介類消費が話題に上がった。とりわけ、ワシントン条約ではクロマグロの国際取引禁止案が議論され、話題騒然となった。そうした議論で日本政府が用いてきた反論のキーワードが、「魚食文化」だった。「魚食文化」を支えるための「伝統的」な漁には問題がなく、今さら規制すべきではないとの主張が展開されたのである。
だが、「魚食文化」という言葉が、あたかも免罪符のように使用されている現実には、多くの疑問がつきまとう。そもそも、現代の「魚食文化」は近代化の過程で形作られてきたものであり、それ以前の伝統的な魚食文化とは明らかに異なっている。
現代における私たちの魚消費の実態とは?
それが伝統的な魚食文化とどう異なっていて、どのような問題があるのか?
私たちが守るべき「ほんとうの魚食文化」を取り戻すための食べ方や暮らしのあり方について考えるきっかけとしたい。
(編集部)
- 退化する日本の魚食事情−自然から遠くなった私たちが失ったもの
上田勝彦 - 流通が魚食を変えた?−魚に触れなくなった日本人
生田與克 - マグロ、銀ムツ、ウナギにサケ−変わる魚食がもたらすもの
井田徹治 - 漁業の衰退を加速させる水産行政の無策
勝川俊雄 - 東京湾が問う私たちの「豊かな」暮らし
大野一敏 - 陸の無関心が海も魚もダメにする
鷲尾圭司
特別記事
斎藤かぐみ
天笠啓祐
細川弘明
連載
- 湯浅誠の反貧困日記 湯浅誠
- 隣のガイコク人 取材・文/大月啓介(ジャーナリスト)
- ゆらぐ親密圏−<わたし>と<わたし・たち>の間 海妻径子
- 音楽から見る世界史 アンゴラ、民族のリズム 粟飯原文子
- Around the World
- オルタの本棚
- インフォメーション