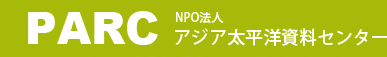PARC TOP>オーディオ・ビジュアル>作品詳細
お米が食べられなくなる日

日本の主食、お米。しかし、生産者は、10年後には日本で米づくりができなくなるかもしれないと語ります。日本の米づくりを追い詰めてきたものは何か、秋田、山形、新潟、埼玉、岐阜、熊本、そして東京の生産と消費の現場を歩き、さらにはメキシコ、タイの農民の声にも耳を傾けながら、米づくりが持つ意味を考えました。
そこで出会ったのは、めまぐるしく変わる政策と、お米の輸入自由化を契機に持ち込まれた競争の論理でした。米の増産を叫ぶ一方で、大量の小麦を輸入してきた政府。お米の消費量が減少すると、一転、生産量を規制する減反が開始されます。1990年代には、お米の輸入自由化が段階的に進むなかでお米の値段が急落。「効率化」の名の下に進められた耕作面積の大規模化は、山国で棚田が多い日本の生産現場に混乱をもたらしました。生産者の収入は減り続け、2007年、時給に換算した稲作農家の労働報酬は、なんと179円。いま政府が進めているTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に参加した場合、90%もの米が輸入米に置き換わると農水省は試算しています。
ビデオは、こうした事実を追いながら、生産者と消費者の思いに耳を傾けます。そして、食糧を貿易することの問題点、自給の意味、食の安全、米づくりを通して見えてきた自然の循環や多様性の大切さについて考え、私たちが大切にしたい価値とは何かを問いかけます。
- 構成
1 稲作の危機と理由
プロローグ
減る米消費と減反
お米の値段と競争原理
理に適わない効率化
揺らぐ自給
2.食糧貿易と食糧主権
輸入自由化の行く末
不安定な生産
貿易が食糧を奪う
3.お米と私たちの未来
私たちが失うもの
ともに支える未来
守り継ぐということ
- DVD/35分
- 本体8,000円+税(図書館価格:本体16,000円+税)
※資料集、作品中の図表がダウンロードいただけます。
- 制作
- 特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター(PARC)2012年
- 監修
- 大野和興(農業ジャーナリスト)
- 構成
- 小池菜採
- 構成・編集協力
- 鈴木敏明
- 取材・撮影
- 菅野春平/堀井 修/京野楽弥子/小口広太/馬場功世/西田 剛/松尾康範/小池菜採
- 撮影
- 鈴木敏明/井上日出男/中村易世/瀬戸山祥子/下島美紗/Stephanie Miller/船山隼人
- ナレーション
- 森田樹優
- 音楽
- 松島美毅子
- 図表デザイン
- 菅原祥子
- ジャケットデザイン
- 武川彦
- 写真提供
- 株式会社OKUTA/秋田県大潟村/NPO法人 メコン・ウォッチ/森本薫子
- 映像提供
- Pesticide Action Network Asia and the Pacific "Rice: the Life of Asia"/The Ecologist Film Unit/KVIE Television "America’s Heartland"/Ricegrowers’ Association of Australia
- 取材協力
- NPO法人 生活工房つばさ・游/ 株式会社OKUTA/ 千葉 保/大久保正明/今野良祐/肥田尚音/日暮郁美/ アジア農民交流センター/ NPO法人 泉京・垂井/ /平柳俊一郎/瀧口智則/若林和彦/若林淳/船山隼人/山本典子/嶋貫章子/安部真理/後藤ふさ子/安部伊立/長津正雄/ /小池由夫/渡邉寛司/岡田和彦/岡田富美子
- 協力
- 岡村 淳/木口由香/飯沼佐代子/横山正輝/松本典丈/市村忠文/近藤康男/上垣喜寛